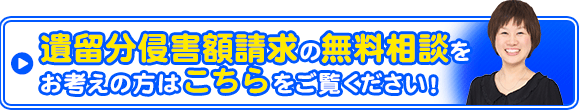遺留分の対象となる財産
1 遺留分の対象となる財産
遺留分を算定する対象となる財産には、どのような種類の財産が含まれるのでしょうか。
今回は、遺留分の対象となる財産について解説していきたいと思います。
遺留分の対象となる財産は、以下のような財産となります。
① 被相続人が相続開始の時において有した財産
② 相続開始前1年以内に贈与した財産
③ 債務の全額
④ 過大な死亡保険金
2 ① 被相続人が相続開始の時において有した財産
相続開始の時において有した財産には、不動産や預貯金、有価証券等が含まれることになります。
この時注意が必要な点として、相続財産には、自動車や貴金属類等の一般的に経済的価値があると判断される財産も含まれる点です。
どのような財産が相続財産に該当するかを正確に判断したい場合には、弁護士に相談することが有用です。
3 ② 相続開始前1年以内に贈与した財産
相続開始前1年以内に、被相続人から相続人及び第三者に対して贈与された財産についても、遺留分の算定対象となる財産に含まれることとされています。
ただし、被相続人から相続人に対して行われた贈与で特別受益(「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」)に該当する贈与については、例外的に10年前に行われた贈与までさかのぼることができます。
簡単なイメージとして、第三者にされた贈与は1年前まで、相続人に対して行われた贈与は10年前までさかのぼることができます。
注意が必要な点としては、第三者に対して行われた贈与であっても、被相続人と第三者の双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」は1年前より以前に遡って遺留分の対象とできる点に注意が必要です。
4 ③ 債務の全額
被相続人が債務を負っていた場合には、「被相続人が相続開始の時において有した財産」及び「相続開始前1年以内に贈与した財産」から債務の全額を控除する必要があります。
そのため、遺留分の主張を行う際には、どのような債務が存在していたのかを明確にする必要があります。
この時、葬儀費用が債務に該当するかどうかが問題となることが多いですが、葬儀費用は喪主が負担するべきであると考えられているため、債務の計算に含まれませんので注意が必要です。
5 ④ 過大な死亡保険金
死亡保険金は、被相続人の死亡によって、生命保険受取人が直接受け取ることができる財産であるため、受取人が相続人とイコール関係ではないことから相続財産に該当しないのが原則とされています。
ただ、「生命保険を契約すれば遺留分を0にできる」とすると、遺留分権利者があまりにも酷な結果となってしまうため、相続財産と比較して過大な死亡保険金が支払われている場合には、相続財産に持ち戻すことが認められる可能性があります。
このとき、どのような要素があれば「過大な」といえるのかが問題となりますが、一般的なイメージとして、相続財産の金額と死亡保険金を比較した時に、死亡保険金が相続財産の価格の50%を超えている場合には、過大と評価される傾向があります。
ただし、実際には受取人である相続人と被相続人の関係や、介護等による被相続人への貢献の有無等、その他の要素を考慮して総合的に「過大」であるかを判断することになりますので、一度弁護士に相談するのが良いでしょう。